間質性肺炎とは
肺はスポンジ状の臓器で、「肺ほう」という名前の小さな部屋の集まりです。肺ほうの中身は呼吸で出入りする空気で、肺ほうの壁の中に血管があり、血液内に酸素を取り込んでいます。
一般的に言う「肺炎」は病気の分類としては「感染症」で、口や鼻から気管を通ってきた細菌が肺ほうの中で炎症を起こし、空気のところに水がたまったりします。
一方で間質性肺炎は、肺胞の壁そのものが炎症を起こす病気であり、原因は感染症ではないことが多いです。炎症が進むと肺胞の壁が厚くなり、硬くなっていく「線維化」が進み、空気の層と血管に距離ができたり、壁自体が固くなって酸素が取り込みにくくなっていきます。

間質性肺炎の原因
間質性肺炎の原因は様々で、リウマチなどの膠原病、職業性のじん肺、カビ・ペットの毛・羽毛など吸い込むことによるアレルギー、薬やサプリメントなどの薬剤性などがあります。
しかし実際には間質性肺炎の原因が特定できない*特発性間質性肺炎の方も多いです。特発性間質性肺炎も専門的にはさらに分類され、その中で最も多いものが「特発性肺線維症」という名前の間質性肺炎です。
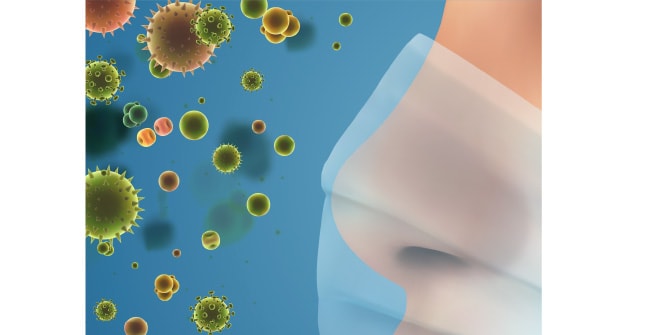
指定難病の特発性線維症
特発性肺線維症は、特発性間質性肺炎の半分以上を占めます。
症状としては動いた時に息切れを感じたり、咳が続くなど他の肺の病気と比べて特別なものではありませんが、聴診をさせていただくと、背中の下の方で息を吸った時にパチパチ、ベリベリという音が聞こえます。
特発性肺線維症は厚生労働省の難病医療費助成制度で指定難病のひとつに指定されています。正確な診断には気管支鏡検査などが必要なこともあり、専門の大きな病院での精密検査が必要です。
間質性肺炎の診断にはCTが役に立ちます。
間質性肺炎の初期の段階では、レントゲンでは変化がわかりにくいものです。
胸部CTは肺を5mm程度に薄切りした輪切りの写真で肺を調べるので、症状が軽い段階でも間質性肺炎の変化に気づけます。
息切れや長引くせきが気になる方、リウマチなどで間質性肺炎が気になる方は、CT検査をご提案します。

豆知識:特発性(とくはつせい)と突発性(とっぱつせい)の違い
医学的に「特発性」とは“他に原因がない、原因不明”などの意味で「原発性」とも言われることもありました。特発性の対義語は「続発性」になり、間質性肺炎であれば、間接のリウマチを患っている経過中に間質性肺炎が起きたり、薬の副反応で起こる間質性肺炎などは「続発性間質性肺炎」になります。
一方で突発性は文字通り突然起こるもので、突然耳が聞こえにくくなる「突発性難聴」がよく知られています。患者さんにとっては「突発性」はイメージしやすいのですが、「特発性」は理解しにくく、混同されることがしばしばあります。



![診察時間:月-金 8時~13時/15時~18時[水曜午後休診]土 8時~12時 休診:水・土 午後/日曜日/祝日](../common/img/p_info_01.svg)
