喘息・アレルギーについて
- 気管支喘息やアレルギー性鼻炎の診断と治療を行ないます
- 喘息の診断と治療効果の判定に有用な呼気一酸化窒素(NO)測定が行えます
- 発作時でも呼吸抵抗が測定できるモストグラフを採用しています
- 喘息の患者さんに多いアレルギー性鼻炎の診断と治療も行います
- 慢性副鼻腔炎の中で喘息の合併が多い指定難病の好酸球性副鼻腔炎の診断と治療について、同じ法人の耳鼻咽喉科クリニックと連携して診療できます

アレルギーとは?
花粉や動物の毛(ふけ)、家のほこり、食べ物などは元々は特にヒトの身体を攻撃するようなものではありません。
しかし、人によってはそれらに対して身体の「免疫反応」が過剰に反応してしまうことがあります。
これが「アレルギー反応」です。アレルギーが関係する病気としては、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどがありますが、呼吸器内科が関わる疾患のひとつが気管支喘息です。
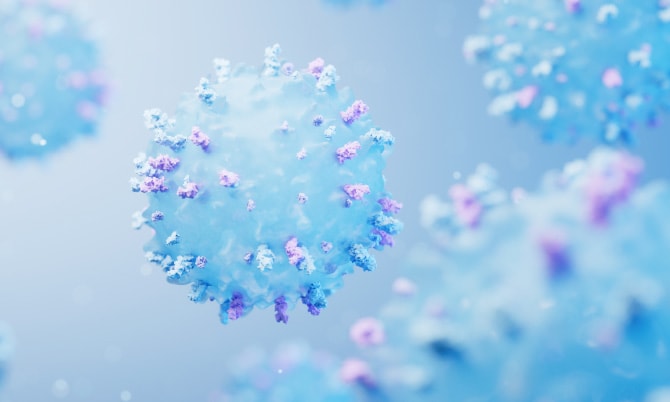
気管支喘息について
気管支喘息は、空気の通り道「気道」の慢性炎症に加えて、発作でさらに気道が狭くなり、せきや痰、息苦しさなどの症状が出る病気です。
喘息発作が起きると、呼吸をする時にヒューヒュー、ゼイゼイといった笛のような音がするのが特徴です。
小児の喘息と成人の喘息では病気のメカニズムが違うところもありますが、アレルギーが引き金になって発作を起こすことが多いです。
しかし全例がアレルギーによるものだけではなく、アレルギー以外にもタバコ、気管支炎などの感染、大気汚染、肥満、運動、アスピリンなどの消炎鎮痛剤の一部、また妊娠などが発作の引き金になることがあります。
タバコは身体のためには誰しも吸わない方がよいですが、呼吸器疾患の観点からは喘息とCOPDの方は禁煙自体が治療になると考えられます。
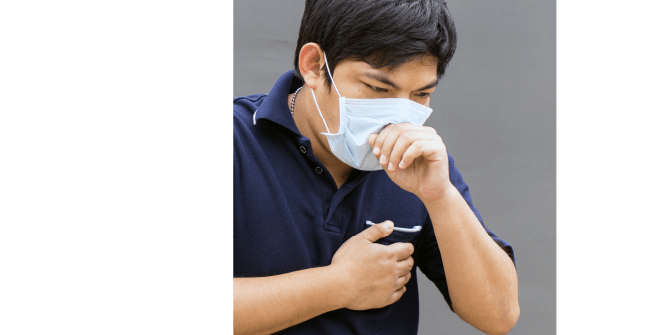
喘息の診断と検査
喘息の診断には症状以外にも肺機能検査で息が吐き出しにくい「閉塞性換気障害」を確認します。実際には肺機能検査は大きく強い呼吸で行なうため、喘息の人、特に発作時は辛い検査になります。
当院では通常の肺機能検査の代わりに、普通に呼吸をしていただくだけで呼吸抵抗が調べられるモストグラフを採用し、苦しい検査をすることなく喘息の診断に役立てています。
また喘息は血液の白血球の一種である「好酸球」が気管支に炎症を起こしていることが知られています。この場合は吐く息の中に含まれる一酸化窒素(化学式NO)が増えることがわかっており、吐く息である「呼気」のNO測定装置で喘息の診断と治療効果判定ができるようになりました。
しかし、呼気でNOが増えない喘息もあるので、実際に採血して好酸球の数を診断の参考にすることもあります。当院では呼気NO測定装置と併せて、院内で好酸球数を測定出来る装置を設置しています。
いずれも当日に検査結果がわかるので、喘息の診断と治療が速やかに開始できる体制を整えています。
咳喘息と気管支喘息
長びくせきの患者さんで「咳喘息」と言われた方も多いと思われます。従来の喘息である気管支喘息のイメージは、「ヒューヒュー」「ゼイゼイ」とした呼吸でしたが、咳喘息ではこれらの呼吸の代わりに咳き込むのが症状です。
呼気NOを測ると気管支喘息と同様に上昇していて、同じように好酸球による炎症が病気の正体と考えられています。吸入ステロイド剤などの気管支喘息の治療をするとせきも治まります。
外来診察をして患者さんに「咳喘息です」とお伝えすると、「今まで喘息と言われた事はありません」と言われることがしばしばあります。
咳喘息と気管支喘息の関係性、つまり咳喘息が繰り返されると気管支喘息になるのかはまだ十分には解明されていませんが、一部の方は移行していくと言われています。
咳喘息の方は治療をすると速やかにせきが治まることも多く、喘息の治療を自己中断してしまう方がおられます。自覚症状が改善しても慢性炎症が続いていることもあり、呼気NOの数値などをフォローしながら治療をつづけていくことが大切を思います。

喘息と花粉症などの耳鼻咽喉科疾患
アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎・好酸球性副鼻腔炎
花粉症を含むアレルギー性鼻炎の方は著しく増加しています。また喘息をお持ちの方でアレルギー性鼻炎を合併されている方も多いことが知られています。
現在では喘息は吸入療法が主体で、またアレルギー性鼻炎については内服薬は点鼻薬が中心になるため、喘息の治療で鼻炎が治ることはなく、並行して治療をする必要があります。
また一般的には「蓄膿」とも呼ばれる副鼻腔炎も喘息の患者さんに合併することが多い疾患です。中でも近年問題になっているのが耳鼻咽喉科の難病に指定されている「好酸球性副鼻腔炎」です。
この病気は成人発症で嗅覚障害を主訴として、両側の鼻茸があるのが特徴です。この副鼻腔炎自体は感染症ではなくアレルギー的な副鼻腔炎とされています。 副鼻腔炎があって血液検査で好酸球が増加していると、この好酸球性副鼻腔炎の「疑い」があります。確定診断のためには鼻茸の組織を採取して、組織中の好酸球を調べる必要があります。
当院では顔面のCT検査で副鼻腔炎の診断ができます。また採血して好酸球の数を測定することもできます。いずれも当日に結果が判明します。
アレルギー性鼻炎や通常の副鼻腔炎の治療は当院でも行ないますが、好酸球性副鼻腔炎が疑われる場合には同じ法人の耳鼻咽喉科いぐちクリニックと京都駅前耳鼻咽喉科アレルギー科クリニックとの連携で診断と治療が行えますので、是非ご相談ください。




![診察時間:月-金 8時~13時/15時~18時[水曜午後休診]土 8時~12時 休診:水・土 午後/日曜日/祝日](../common/img/p_info_01.svg)
